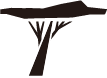「夢にては聞こゆる聾の夜長かな」
「目覚むれば元の聾なり菊枕」(聞く、とかけてある)
「炭火埋め怒りを埋めいたりけり」
子供の頃、私は、26軒の村の住人の顔と名はだいたい把握していました。でも、一度も話したことのない人がいました。それがこの俳句を残した若い女性です。彼女の姿は何度も見かけましたが、いつも無表情で、静かにたたずむその姿は別の世界に住むかのようでした。鄙(ひな)には希な気品があり、子供の私には挨拶するのさえ憚れたのです。
この春、帰省して、たまたま彼女の遺稿句集を実家で見つけ、興味深く読みました。そして、ストマイ禍で耳が不自由になり、脊椎カリエスで入退院を繰り返していたこと、1969年2月22日34歳で病死したことなどを初めて知りました。私が中学3年の時です。
「菊に立ち生涯ひとりかと思ふ」
「振り向けば吾れ一人なり秋の暮れ」
この句は孤独がにじみ出ています。しかし、読み進むと、彼女には村とは別の世界が三つあったことが知られました。一つは俳句仲間、もう一つは目の不自由な人々との交流です。
「春寒を手に覚えつつ点字打つ」
「すぐ冷ゆる手をかこちつつ点字打つ」
耳の不自由な自分が目の不自由な人役に立つことを喜びとしていたようです。
そして、三つ目が聖書の世界です。
「教会へ軒伝い行く朝時雨」
「やつれゆく手もて開きし聖書かな」
「生きることの尊さに触れ霜の夜」
私が本格的に聖書に触れたのは、彼女が召されて3年後のことです。あの時代、あの山里で、不治の病を背負った女性がこんな世界を開いていたなどとは、夢にも思いませんでした。
「着ぶくれて死なねばならぬ命守る」
これが彼女の辞世の句となりました。これは、若くして死んでいく儚い命をいとおしむ句ではありません。なぜなら、「命守る」のは本人ではなく、キリストなのです。
私の村にこんな女性がいたことに深い感動を覚えました。
「やがて発つ丹波は栗の花ざかり」この句に送り出されて郷里をあとにしました。